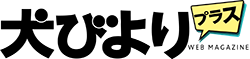さまざまな手術や病気などで、愛犬に輸血が必要となる場合も少なくない。輸血の際に必要となる血液はどのように集められているのか。いざという時のためにも詳しく知っておこう。
血液の役割

人間でも犬でも、血液は全身を巡っている。血液は生命を維持するために欠かせない多くの役割を担っている。それだけにとても重要なものだ。
血液が造られるのは、骨の中心部にある骨髄という組織。骨髄で血液中に含まれる水分が造られたのち、血管を通じて全身を巡るのである。
血液中の水分はおおまかに、液体成分の「血漿」と細胞成分の「血球」に分けられる。
血液中の約55%を占めているのが液体成分の「血漿」である。二酸化炭素を肺へ運んで体外へ放出したり、必要な栄養成分を体内の組織に運んだり、不要な老廃物を運ぶなどの役割をしている。
残りを占める細胞成分の「血球」には。赤血球や白血球、血小板などがある。これらもそれぞれ重要な役割を持っている。
「血球」の中に一番多く含まれているのが赤血球。主な働きは、全身に酸素を運ぶこと。
次に多いのが血小板。傷ができた時などに血液を固める(血液の凝固作用)働きをしている。
白血球は、外部から進入した細菌やウイルスなどから、身体を守るための免疫作用を司っている。
このように血液中に含まれる成分はそれぞれが欠かせない役割をしているため、何らかの原因で1種類でも減少したりすれば、体に影響を与えてしまうのである。
人間と同様、犬の体内に占める血液量は体重の約8%といわれている。例えば、体重10kgの犬であれば約800ccの血液量が体内に占めているということ。そして、体内の血液は3分の1を失われると命に関わるのだ。
そのため、大量に血液が失われた際には、輸血が欠かせなくなってくる。
犬の血液型判定法

輸血をするにあたって、人間でも血液型などが適合しなければならないが、それは犬でも同じだ。どの犬の血液でも輸血できるというわけではない。
併血犬(血液を提供するドナー)と輸血犬(輸血を受けるレシピエント)との血液が適合していなければならない。適合しなければ、副反応が出て、場合によっては命に関わる。
適合する血液であれば、同じ犬種からしか輸血ができないというわけではなく、違う犬種でも輸血は可能である。
犬の血液型は、DEA(犬赤血球抗原)という、赤血球の表面に存在する抗原タイプによって分類され、9種類以上あるといわれている。
その中で、輸血時の副反応を起こす性質が高く、臨床的に重要なのがDEA1.1。血液型の種類として測定できるのが、DEA1.1の+(陽性)か-(陰性)ということだ。
いってみれば、犬の血液型はおおまかに分けると、DEA1.1+またはDEA1.1-の2種類となる。
犬種や遺伝によって、どちらかの方が多いという違いはあるが、日本にいる犬は+の方が多く、60%を占めているそうだ。
また、例え血液型が同じであっても、副反応が絶対起こらないとは限らない。より詳しく適合するかどうかを調べるためには、併血犬と輸血犬の血液を混ぜて判定するクロスマッチテスト(交差適合試験)を行っていくことが必要となってくる。
輸血を行う前にはこのようにして、血液型の判定やクロスマッチテストを行い、適合性を調べていくのである。
輸血が必要な犬の病気

どんな手術においても輸血が必要となるわけではなく、手術の種類によっては違いがある。輸血が必要となる手術には次のようなケースが多い。
ひとつは、血液の凝固系に問題がある手術の場合。本来なら、血液中の血小板は傷ができた時などに、出血を多くしないため血液を固める作用を持っている。その作用に問題があれば輸血が必要となる。
また、出血が大量に出ると予測される手術の場合。例えば肝臓がんの摘出など。肝臓が悪くなっていると、出血傾向が高くなり、血も固まりにくくなっている可能性がある。
交通事故などで大量出血がある場合も必要だ。
治療として輸血が必要となる主な病気としては次のような場合がある。
【免疫介在性溶血性貧血】
免疫システムに異常が起こり、赤血球が破壊される病気。感染や腫瘍が原因になる場合と、原因不明なこともある。主な症状は、元気がなくなる、ふらつく、貧血を起こすため口や陰部の粘膜、目の白目部分などが白っぽくなる、など。免疫抑制剤などを使い経過を見ていくが、重症の場合は輸血が必要。
【血小板減少症】
血小板の数が減ってしまう病気。骨髄や脾臓の異常が原因になる他、免疫介在性のものなどがある。主な症状には、全身の紫斑、吐血、傷口の出血が止まりにくい、など。その他に、血尿、血便、鼻血などが見られることもある。治療には原因となっている病気の治療と併せ、免疫抑制剤の投与や輸血を行う。
【播種性血管内凝固(DIC)】
ガンや重度の感染症など、すべての病気で重篤な症状をあらわすのが播種性血管内凝固だ。多臓器不全を起こす前の段階であり、固めたり、溶かしたりするバランスが血液凝固のバランスが崩れてしまう。臓器の中に小さな血栓ができ、そのままにしておけば血管を塞いで命を落としてしまう。元の病気の治療とともに、崩れた血液凝固のバランスを戻すために輸血が必要となる。
血液の採取

・1~7歳程度の健康な成犬
・過去に輸血経験がないこと
・狂犬病やワクチン接種を行っている
・フィラリア予防をしている
・感染症を発症していないこと
・妊娠していない
街中などで、輸血の協力を呼びかけているのを見かけたことはないだろうか。人間の場合は、献血で集めた血液を保管しておき、輸血用血液を必要としている医療機関へと供給するシステムが整っている。
しかし、現在の日本では、人間の血液バンクのような組織は、犬をはじめとする動物のためには存在していない。そのため、輸血が必要となった場合、輸血用の血液は各々の動物病院で確保していくしかない。
動物病院内で飼育している犬を併血犬として管理するか、一般家庭で飼育されている犬に併血犬として登録制度を行い、協力してもらう方法をとっていることが多い。
「輸血を必要としている犬がいるならば、ぜひ助けてあげたい、うちの犬を併血犬として協力してあげたい」と思う飼い主さんも少なくない。
だが、血液を提供するにあたっては、どんな犬でも大丈夫というわけではない、さまざまな条件を満たしてあげることが必要だ。しれらの項目は上に書いた通りだが、これは必須条件となる。
まずは、もちろん健康な犬でなければならない。年齢は1~7歳が理想。過去に輸血を受けた経験があると、他の血液が入ってきたことで血液に抗体が出来ているため、併血はできない。また、併血犬が伝染病や伝染病にかかっていない点もとても重要だ。
妊娠中の犬は、体の中でさまざまな抗体ができているため、併血には向かないといわれている。この他にも、採取にあたっては貧血をおこしていないかなどを事前に調べておく必要がある。
そして、一度併血をした犬は、貧血を起こさないためにも、3週間から1ヶ月は間隔をあけなければ、併血はできないことになっている。
これらの条件を満たしている犬が併血犬となり、輸血用の採血を行っていく。
主に頸静脈から採血するのだが、おとなしい犬なら無麻酔で行うが、暴れてしまう犬の場合は沈静や麻酔をかけてから行うことになる。
輸血のリスク

血液検査やクロスマッチテストを行い、適合した血液であっても、犬の血液の中にはいろいろな因子があるため、輸血による因子が全くないとは言い切れない。
場合によっては、適合した血液を輸血しても副反応が出ることがある。飼い主さんは、輸血を行うときはリスクが伴うことを覚悟しなければならない。
輸血で行う副反応にはいくつが種類があるが、大きく分けると、免疫性のものと非免疫性のものとがある。
また、免疫性、非免疫性のそれぞれで輸血中や輸血数時間に以内に起こす急性のもの、しばらく経過した後に起こす遅発性のものに分けられる。
急性免疫性の副反応には、まず赤血球が破壊されてしまう「急性溶血性輸血反応」がある。これは通常、初めて輸血を経験する犬には起こりにくいといわれている副反応だ。しかし、過去に妊娠・出産経験がある、ワクチン接種などでアレルギー反応を起こしたことがあるなどの経歴をもつ犬は発症する可能性が高くなる。他には、かゆみやじんましんが起こり、重度の場合は呼吸停止や心肺停止などのアナフィキラシーショックを起こす「アレルギー反応」。発熱が見られる「非溶血性発熱輸血反応」。肺水腫、発熱、低血圧などの症状が見られる「急性肺障害」などがあげられる。
遅発性免疫性の副作用としては、赤血球が破壊される「遅発性溶血性輸血反応」の他、輸血してから1~2週間後に血小板が減少し、皮下出血(紫斑)が起こる反応もある。
急性非免疫性の副反応もさまざまに考えられる。輸血する際の速度が遅すぎる、必要以上に輸血量が多いなどの場合、心肺数低下、腹水、胸水、肺水腫、チアノーゼ、呼吸困難などを引き起こすことがある。冷温保存した血液は37℃に温めてから輸血するが、温めずに輸血すると「低体温症」を引き起こしてしまう。輸血用血液に細菌感染があれば、重篤な場合、「敗血症」を起こす可能性もある。
遅発性非免疫性の副反応には、もし感染症疾患を持った犬の血液を輸血してしまった場合、「感染症」を起こす可能性がある。
未然に防ぐためには、併血犬が感染症を持っていないかを検査で調べることが大切だ。
犬の輸血 まとめ
いかがだっただろうか。輸血に関しては、この犬種だから特別にこれに気をつけなければならないということはなく、どの犬種でも同じと考えていい。
あらかじめ愛犬の血液がDEA1.1の+なのか-なのか知っておくと、万が一輸血が必要となった際に役立つだろう。
輸血にはリスクもともなうことを忘れてはいけない。
だが、輸血をしなければ命の危険があるとなれば、どうしても行わなければならない場合もある。
少しでもこれらの知識を入れておくことが愛犬の命を守るためにも大切だ。
人気のキーワード:
#しつけ #ごはん #シニア犬 #健康管理
#性格 #散歩 #気持ち #病気 #おでかけ
#ケア #子犬 #性別
コーギースタイル Vol.33『輸血の話』より抜粋
※掲載されている写真はすべてイメージです。