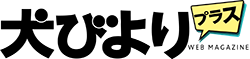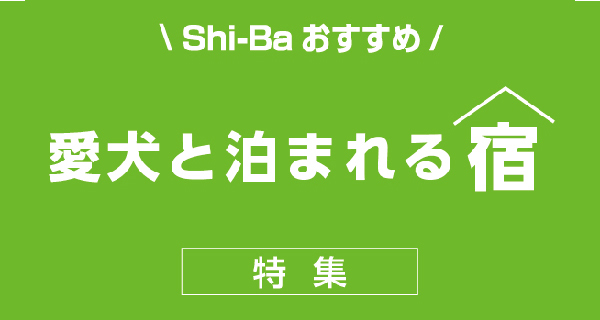オスワリ、マテ、オイデ……。日常何気なく使っている愛犬への「声かけ」。けれど、うまくいかないこともある。「うちの子は言うこと聞かない!」と思う前に、その声かけ方法が正しいのか、一度見直してみませんか?

私は、犬種で声かけの入りやすさが違うと感じたことはないんです」としつけインストラクターの長谷川先生。
「例えば、オスワリという声かけを覚えるかは、犬種の違いで差が出るというよりも飼い主さんの教え方や伝え方にかかっていると思います」
柴犬に限らず、犬は聴覚より視覚に入るものに反応しやすい。「オスワリ」と声をかけられた時に、そばで動くものがあれば、そちらに気を取られる犬は多いのだ。「犬は声のトーン、動作、雰囲気などをまとめて覚えていることが多いんです。
だから、いつもは優しいトーンで『オイデ』と伝えているのに、例えば愛犬が脱走してしまった時に必死になって『オイデー!』と叫んでしまったら、犬にとっては〝あれ、これは違うぞ〞となってしまいます」
また、子犬の頃は無邪気にやっていたことでも、さまざまな経験を積んで犬が「これは苦手だな」と感じるようになると、それに対しての声かけには応じにくくなる。その様子が声かけ拒否に見えることもある。
「子犬の無邪気さを残していて、何でも素直に応じる子もいますが、日本犬は精神的に成長して〝ボクはコレが苦手かも〞と気づくタイプが多いように思います。それが【日本犬は声かけが難しい】と言われる理由のひとつなのかもしれませんね」
日本犬の声かけ事情①繊細な性格の子が多く周囲に気が散りやすい
特に柴犬は繊細なタイプが多く、周囲の環境の変化を敏感に察する。言い換えれば、周囲に気が散りやすい。他のにおいや音などに気を取られてしまいがちなのだ。

やりがちNG
家族間で声かけの方法が違う
お父さんは低くぼそっと言う、お母さんは高い声で早口など、トーンや声色が違うと犬は混乱しがち。特に男性の低い声よりも、女性の高めの声のほうが犬には通じやすい。男性はなるべく明るいトーンを心がけ、適度な速度ではっきりと声かけするよう、家族で統一を図ろう。
やりがちNG
「ハイ」や「ヨシ」を冒頭に付けている
「ハイ、オスワリ」「ヨシ、オテ」など冒頭に単語を付けてしまう飼い主さんもいるが、声かけの最初の一音がすべて同じだと犬は混乱する。特に「ヨシ」が、「マテ……ヨシ!」のようにその状態を解除する言葉としても使われていると、余計に判別がつかなくなってしまう。
日本犬の声かけ事情②前提として犬は聴覚より視覚に反応する
柴犬に限らず、犬は耳から入る音よりも、目で見えるものに反応する。飼い主さんが手や体を動かしているとそちらに気を取られ、声かけに反応しなくなる。

やりがちNG
やりがちNG 長めの文章でだらだらと声かけする
「いい子ね~、オスワリしましょうね~」など長めの文章で声かけしてしまうと、犬には要点が伝わりにくく、声かけが通らないことが多い。また、声かけの間に注意が散漫になることも。短い単語ではっきりと、飼い主さんがしてほしいことを伝えるのがベスト。
やりがちNG
やりがちNG 犬の名前を呼んで叱っている
「○○、ダメ!」のように、名前を呼んで叱っていると名前にマイナスイメージが付きやすい。名前を呼ばれても「どうせ嫌なことがある」と覚えて、反応しなくなることも。名前を呼ばれたらほめられる、いいことがあると教えたほうが、愛犬とよい関係をつくることができる。
日本犬の声かけ事情③柴犬は精神的に大人になる子が多い
子犬の無邪気さを残す犬もいるが、日本犬は“大人”になる子が多い。経験から自分の苦手がわかってきて、「これは苦手」と主張するようになる。それが“扱いづらい”という印象を与えることも多い。

やりがちNG
犬が緊張する場面で猫なで声を出す
例えば、犬が苦手とする動物病院で飼い主さんがいつもと違う猫なで声で「大丈夫よ~」と声かけをする。それだけで犬は「いつもと違う」という思いを強め、さらに緊張する結果になる。犬が緊張しそうな場面はあえて普段と同じトーンで声をかけてあげたほうがよい。
次回「コマンド編」をお届け!
監修:長谷川あや甫 先生
家庭犬しつけインストラクター。PARA主宰。優良家庭犬普及協会常任理事。GCTジャッジ。AFC公認インストラクター。福島県を拠点に全国でしつけ指導、講演、執筆活動など、幅広い分野で活躍中。
いぬのしつけ方教室・ようちえん PARA
☎0242-85-8896
https://paradoggy.com
Text:Eriko Itoh
Photos:Mariko Nakagawa、Michio Hino、Miharu Saitoh
Shi-Ba Vol.135『「言うこと聞かない!」のその前に 声かけ見直し塾』より抜粋