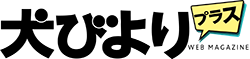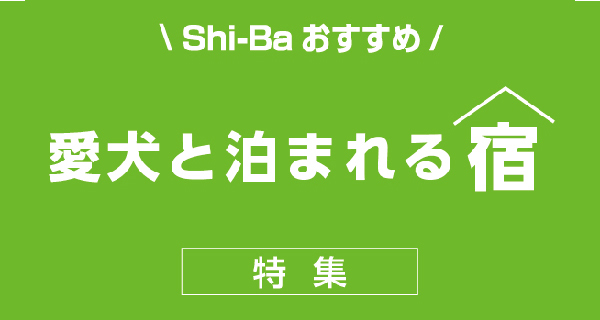本気出せばハードルもちょろい!
「走りたい」「動きたい」は、犬の本能。
1日のほとんどをヘソ天で寝ている日本犬だって、実は運動が好きなのだ。
ただし、人の暮らしに合わせて生活していると自由に体を動かす機会は減っていき、運動の楽しさまでも忘れてしまうことがある。
愛犬の心身の健康を守るため、運動にまつわるあれこれを知っておこう。

飼い主さん、早く指示出してくれる?
「楽しみたい」が運動のモチベーション
運動好きな犬といえば、スポーツ万能なボーダー・コリーや短い足でパワフルに走り回るウェルシュ・コーギー、水を見ればバシャーン!と飛び込まずにいられないレトリーバーなどが頭に浮かぶ。残念ながら日本犬は「スポーティな犬」のイメージに当てはまるとは言えない。
ただし、だからといって日本犬が運動を嫌いなわけではないし、もちろん苦手でもない。走る姿は最高にかわいくてかっこいいし、その気になれば、ジャンプだって水泳だって上手にできるのだ。
スポーツ好きなイメージが定着しないのは、ドッグスポーツが飼い主さん主導で行うものだからではないだろうか。自分の判断に従って行動する賢さは日本犬の大きな魅力だけれど、人の指示に瞬時に反応することが求められるドッグスポーツでは、不利に働くこともある。結果的に他犬種に勝利を譲ってしまうことが多いため、スポーツの世界で日本犬の能力を十分にアピールすることができないのだろう。

かっこいい? うん、わかってる
でも、スポーツの意義は勝つことだけだろうか? 五輪だって、「参加することに意義がある」といわれている。スポーツにおいて大切なのは、結果ではないはず。そこに至るまでの過程や、運動を通した心身の成長にこそ価値があるのだ!
……というわけで、日本犬にはまず、「楽しむための運動」をおすすめしたい。競技などの上達以上に大切なのは、犬が楽しむこと。飼い主さんは、愛犬に「もっと一緒に遊びたい」と思ってもらえるように、関わり方&教え方を工夫していこう。

そのハードル、下をくぐるの?
運動の一環としてアジリティを取り入れる!
アジリティの楽しさは、愛犬との一体感を味わえること。
練習を通して、跳ぶ、くぐる、バランスを取るなど、さまざまな動きを体験することができる。
そもそもアジリティってなに?
人と犬がペアになって行う「障害物競走」のようなスポーツ。コースには、複数の障害がさまざまなパターンで設置される。人の指示に従って犬が決められた順序で障害をクリアしていき、正確さとタイムを競う。犬には運動能力に加えて人の指示を聞き分ける力、人には適切な指示を出す力が求められる。
体の大きさによって、4つのクラスに分けられる。
・S:体高35cm未満
・M:体高35cm以上43cm未満
・IM:体高43cm以上48cm未満
・L:体高48cm未満
やって楽しい、見てかわいいドッグスポーツの花形
アジリティには、次の9種の障害が使われる。
①トンネル
②ハードル
③スラローム
④ロングジャンプ
⑤ウォール
⑥タイヤ
⑦シーソー
⑧Aフレーム
⑨ドッグウォーク
競技会で使われる障害はすべてサイズが決められており、ハードルなどジャンプして越えるタイプの障害は、カテゴリーに応じて高さが調整される。
また、⑦〜⑨の障害には、犬が必ず踏まなければならない「コンタクト・ゾーン」が設定されている。9種類すべての障害を使うものを「アジリティ」、難易度が高い⑦〜⑨を含まないものを「ジャンピング」と呼び分けることもある。
競技は、全長100〜220メートルのコースで行われる。人と犬が同時にスタートし、人の指示に従って、犬が障害をクリア。レースごとに設定される「リミットタイム」以内にゴールしなければならない。障害の順序を間違えたり、リミットタイムを超えたりすると失格となる。
障害の配置の仕方やルートはレースごとに異なり、スタート前に人だけが下見をすることができる。犬自身がルートを覚える機会はないので、犬の動きを人がいかにうまくコントールするかが勝負の決め手だ。

①トンネルは直径60cm。3~6mの長さで設置され、途中でカーブしていることも。

②競技会の際のハードルの高さは、Mクラスで35 ~ 40cm。バーを落とすと減点される。

③ハードル初挑戦のつくねは、地面に置いたバーをまたぐところからスタートし、数分で飛び越えられるように。

④ティベリウスは、競技会で優勝経験もあるベテラン!

⑤トンネルの練習は、出口側でオヤツを持った飼い主さんに呼んでもらうところから。

⑥60cm感覚で並べられた12本のポールを、左右から交互に回り込むように走るスラローム。

⑦頂点170cmの坂を上って下りるAフレーム。高さを怖がる犬も多いとか。
アジリティを始めるには?
日本犬ってアジリティに向いている?
洋犬に比べて胴が太めな日本犬は、残念ながらアジリティ向きのスタイルの持ち主とは言えない。でも、きちんと教えれば、すべての障害をクリアできるようになる能力をもっていることは間違いない。
アジリティを楽しめるのはどんな性格の犬?
一番のポイントは、飼い主さんとの相性。飼い主さんを信頼し、一緒に遊びを楽しめる犬はアジリティの上達も早い。警戒心が
強く、障害を避けたがるタイプの場合は、楽しませる工夫をしながら教えよう。
アジリティを始める前に身につけておきたいことは?
最低限の社会化は必要。競技はもちろん、練習も他の犬がいる場所で行うことが多いため、知らない犬や人に対してむやみに吠えたり飛びついたりするような行動は制御できるようにしておきたい。
練習場所やトレーナーはどうやって探す?
口コミやインターネットなどで探す他、競技会(見学は無料のことが多い)を見に行くのもおすすめ。スクールの関係者やトレーナーも来場しているので、気になるところがあれば話を聞くことができる。
編集部公式SNSでは本特集撮影時の3匹の勇姿を動画でご紹介!ぜひチェックしてみてください♪
監修:若林匡智先生
SJDフレンズドッグクラブ チーフトレーナー。
JKC公認訓練士、OPDES公認プロフェッショナルトレーナー。アジリティのレッスンを中心に、家庭犬のしつけも行う。アジリティ競技会の審判も務め、日本代表としてアジリティの世界選手権への出場経験もあり。
https://www.sjd.co.jp/dogclub/
Text:Kumiko Noguchi
Photos:Teruhisa Tajiri
Models:Tiberius、Tsukune、Vipsania
Shi-Ba Vol.135『愛犬と一緒!だから楽しい運動の極意』より抜粋