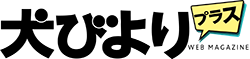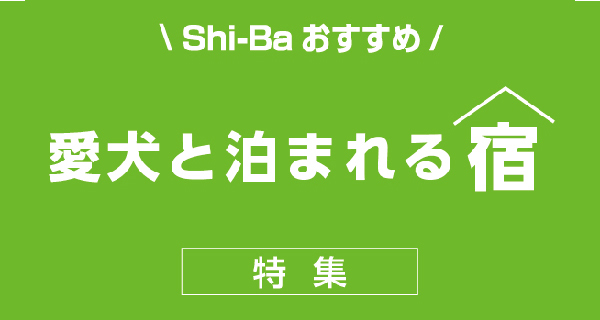犬が来ても人が来てもバイクが来ても! 風でビニールや木の枝が揺れても!ビクッとしたり腰が引けたり、固まったり。その度に飼い主たちは思うのだ。
「うちの子はビビリかも……」でもそれってホント? いったいなぜ? を、徹底分析!
これがビビリの定義だ!
本特集では不特定の対象について、幅広く警戒する、不安がることを総じてビビリと言う。特定のものにのみ怖がる、苦手なものがあるという場合は、ビビリとは言えないのだ。
なんでもかんでもとにかく怖い
物理的
雷や掃除機などの大きな音、得体の知れない大きな物体に対する恐怖、また動く物体の予測不可能な動きなどに不安と恐怖を覚えてしまう。
社会的
子犬時代に犬や人間に接する経験や機会(社会化)が少ないと、コミュニケーションの方法がわからず、好奇心より恐怖心が勝ってしまう。
ビビリになってしまうワケ
ビビリなのは生まれつき? 日本犬の特徴?それとも暮らしている環境のせい?
ビビる理由は複数あり、それぞれが互いに関係し合うこともある。
遺伝
親がビビリだと子もそうなりやすいといった生得的要素は少なくない。刺激閾値が低いとわずかな刺激にも犬が強く反応してしまう傾向があるためビビリになりやすい。
警戒心
犬にとって、危険なものに対する用心深さや危険を察知する能力は生き延びるために本来必要なもの。そうした警戒心が必要以上に強くてもビビリやすい。
学習
子犬時代に社会化が適切になされなかった(必要な学習の不足)、もしくはその時期に、怖い思いや嫌な思いをした強い記憶があると(不安・恐怖の学習)、ビビリやすい。
+(プラス)
予測できない恐怖
経験にない、予測できないという状況は、犬に不安や恐怖を感じさせ、慎重な行動をとろうとさせる。ビビリな子はより強い反応をしやすく、予測できない状況を避けようとする。
マイナス思考
日本犬は一般的に、この先何か嫌なことが起こるかもしれないという不安や恐怖を察知しやすい、もしくはそう考えやすい傾向があり、それに対し逃げよう避けようとしがち。
すぐ驚く、固まる、怖がる…… それってビビリ!?
最初にお伝えしておこう。うちの黒柴(オス・4歳)もビビリだ。二匹目の犬なので大した比較はできないが、最初の犬は似たような形の洋犬で、普段は何事にも動じない(無関心とも言う)けれど、けんかを売られたら買ってしまうようなところもある強気なキャラでもあった。
ところが今の子ときたら、音、物、人間、そして犬、あらゆるものにビクつくわ、散歩中は後ろから何か迫ってこないか確かめるため十歩歩いては振り返るわの繰り返し。好意的に近寄ってくる犬からも逃げようとするため「すみませんねえ、うちの子はビビリなんで……」と言い訳をして立ち去る日々なのだ。
「特定のものや刺激を嫌がったり怖がったりするだけなら、決してビビリではありません。例えば高所恐怖症の人も他の場面でなんでもなければ臆病とは言いませんよね。怖がるものがあるからと、愛犬がビビリと決めつけないほうがいいですよ」
そう教えてくれたのは、犬の行動学に詳しい堀井隆行先生。
「まあ、なんでもかんでも怖がるなら真性のビビリかな」……やはりうちは、ほぼなんでも怖がるから真性のビビリかも。
ビビリの反応
反応のバリエーションや程度は、犬によってさまざまだ。愛犬はこのうち、どれにあてはまるだろう。
どんな時で、普段とどれほど違うのか、その見極めも大切だ。
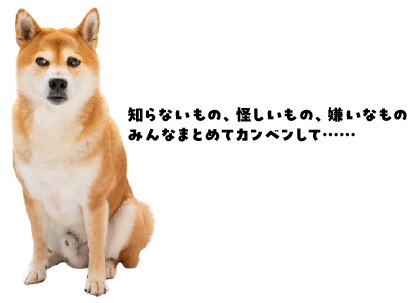
ビクンとする
普段と違う音や物に体をビクンとさせる筋収縮反応の一種。その場限りで終わることが多い。
固まる、うずくまる
じっと動かなくなる。耳を後ろに引き、腰を低く、尾を巻き込むことも(緊張性不動化)。
隠れる
ケージやクレート、家具の隙間など自分が安心できる所に一目散に避難してやり過ごす。
跳ぶほど驚く
驚愕反応といって、強く驚くことによって反射的に跳び上がってしまう行動。
逃げる、遠ざかる、避ける
不安な・怖いものからできるだけ離れて、逃げて、関わらないようにする。
専門家に相談がおすすめの反応
おもらし
恐怖による失禁・脱糞。日本犬はいわゆる「うれしょん」より「ビビリしょん」のほうが多い。
震える
ガクガクブルブル、全身を細かく震わせて止まらない。かなり怖がっている。
吠える(叫ぶ)
日本犬は強い恐怖を感じると、吠えるというよりも高音でキャーーーンと叫ぶ場合が多い。
パンティング
普段の呼吸と違い、ハアハアと息が荒くあえぐような呼吸になる。よだれをダラダラ垂らす場合も。
飼い主に必要なのは犬の反応の見極め
ビビリとひと口に言っても、その反応や様子は下記のようにさまざまだ。いずれもパッと見ただけなら、「あ、ビビってる」という印象を受けるが、本当にそうだろうか。
例えば何か目新しいものに出会って、じっと動かなくなってしまった犬がいたとする。それは、「未知のものに対して冷静に情報を収集、分析している最中」なのかもしれない。
この場合は、どうすべきか自ら判断を下すまでは理性的に「動かない」でいるのだ(たとえ、多少腰が引けていたとしても)。その後、危険と判断すれば避けようとするし、そうではないとわかれば近寄っていく場合もあるだろう。
一方で「未知のものに対して強い不安や恐怖を覚えた」ことで、情動的に「動けない」犬もいる。これはビビリの反応である。緊張性不動化といい、いわゆる腰が抜けた状態に陥っている可能性が高い。この状態の犬は怯えた表情をし、固まってしまう。飼い主なら普段の様子からどちらなのか見極められるだろう。
「日本犬は、危険に対する予測能力が高いゆえに慎重な犬が少なくありません。それがビビリと誤解されている面もありますね」と堀井先生。
日本犬は賢いからこそビビリやすい!?
反応とは瞬時のもの。こうした反応を繰り返す犬でも、未知の刺激に警戒しやすいタイプや、慣れるのに時間がかかるタイプなだけかもしれないので一瞬の反応だけで決めつけないようにしたい。特に日本犬は危険予測を瞬時に立て、避けようとする能力が高い。「慎重」や「警戒」の要素を、「臆病」と誤解されやすい犬種でもあるのだ。
ビビリが刺激に感じるモノ
犬が怖がるもの、不快に感じるものはある程度決まっている。周囲によくあるものでも、普段とは違う音や動きに出会うと、自分によくないことが起こると感じてしまうことも。
「普段と違う物、音、人」は苦手なんだってば!
大きな音
雷や花火などの破裂音、車のエンジン音、金属がぶつかる・こすれ合う音、ビュービューという風音や、枝や物がバサバサするなどの音は苦手。
大きな物
自分より大きくて、かつ見慣れないものは、警戒心を抱かせる刺激のひとつ。例えば大きな荷物や長い棒、大きく奇妙な置物などに反応する。
スピード感
傘を開く時のように音と勢いが同時に出るものや、車やバイク、自転車など音とスピードを伴って迫ってくるものは恐怖の対象となる。
総じて生き物として身の危険を感じる「強い刺激」
ビビリが怖いモノ
ビビリは、怖い経験をした場所、初めてのもの、知らない人など、普段の環境の安定性が崩れることに弱い。
あくまでも一例だが、ビビリ犬あるある対処法をご紹介。
動物病院
動物病院が苦手な犬はビビリに限らず、少なくない。予防接種や自由が効かない診察の場という経験から、嫌な場所として記憶されてしまうからだ(恐怖条件づけ)。また、飼い主が緊張していたりすると、それを敏感に察して、怖がることも。
嫌な場所ではないと慣れてもらうのが第一
動物病院は必ず行く必要のある場所だからこそ、そこへ行くことが非日常ではないことをわかってもらう必要がある。前を通る散歩コースにしてみたり、スタッフさんからオヤツをもらったりして、嫌な場所ではないと根気よく慣れてもらおう。それでも怖がる場合は往診という最終手段もあるので検討してあげたい。
ドッグラン
散歩の時に他の犬が興味深そうに近づいてきても、見てみないふりをしたり、腰が引けてしまうようなビビリにとって、数多くの犬が元気よく走り回るドッグランは、よりハードルが高い。とてもではないけれど連れて行けない!?
リードがない状態がうれしいことも
まずはドッグランを見物するところから始めて様子を見よう。誰もいない時間に一番乗りして自由にさせてみるのも手。実は、散歩ではリードにつながれている→自由に動けない→怖い、のに対し、自由に動ける→どこにでも行けるし逃げられると感じ、ドッグランでは元気にかけ回るビビリも存在するのだ。
知らない人
飼い主以外の人を警戒したり、怖がることも多いビビリ。家族に子供がいない場合は、大人に比べて予測不可能な行動をとったり突然大きな声を出したりするために苦手な子は多い。普段接していなければ、年配の人を怖がる犬も。
飼い主はいつもと変わらぬ態度で
いつもと違うことが起こると不安になるのがビビリ。対人間も同様で、普段接していないタイプとはどう対応していいかわからないからビビるだけで、興味がないわけではない。飼い主がいつもと変わらぬ態度でいると次第に慣れることが多い。怖がるからと緊張して焦って抱っこなどすると逆効果になるので注意。

\日本犬の長けた能力/
「ここは怖くない場所」と場面設定を区切る能力
日本犬は、安心できる場面とそうでない場面との認識能力も高い。例えば同じビニールがバサバサと不穏な音を立てても、安心できる室内では特に怯えず、安心レベルの下がる外では「危険な音かも」と警戒をするという具合だ。細かな判断や区別ができる日本犬、すごいぞ!
ビビリは、克服するのではなくどう付き合ってあげるかが大切
1歳までの子犬なら社会化が何より大切だが、成犬になってからではそうしたトレーニングの効果が出にくくなるのはご存じだろう。
「とはいえいくつになっても犬は学習する動物です。実際、精神的に成熟してくる2〜3歳くらいになると、子犬の頃よりもその子なりにビビリ方が落ち着いてくる犬は多いです。反対に、8〜9歳を過ぎた頃から加齢性に伴う不安になりやすさからビビリが出てくることもあります」と堀井先生。
飼い主に求められるのは、その子のビビリの特徴の見極めと、避けられるものは避けてあげること。
例えば散歩で家から遠く離れるのが苦手な犬なら、安心できる手近なコースを数周回るだけでいい。飼い主が欲張らないことも大切なのだ。
そしてクレートトレーニングなどをして、犬が不安を感じた時に安心して逃げ込める場所を用意してあげること。
犬のちょっとした反応をビビリと拡大解釈する必要もないし、嫌がるもので避けられるものに無理に慣れさせる必要もない。もちろん怖がる様子を面白がったり叱ったりするのは絶対NG。ビビリ犬にとって一番の頼れる安全基地は、飼い主なのだから。
堀井隆行先生
ヤマザキ動物看護大学動物看護学部動物人間関係学科講師。愛玩動物看護師。動物のストレス管理や行動修正を研究し、講演活動や動物病院での行動カウンセリングも行う。共著に『知りたい! 考えてみたい! どうぶつとの暮らし』(駿河台出版社)。
Text:Asako Shinohara Photos:Minako Okuyama Illustrator:Yuko Yamada
Shi-Ba Vol.134『慎重ゆえに勘違いされがち…… 今こそ!ビビリ大解剖』より抜粋