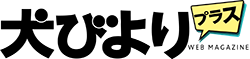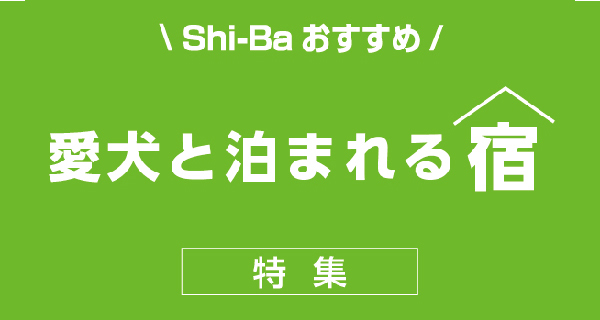「走りたい」「動きたい」は、犬の本能。
1日のほとんどをヘソ天で寝ている日本犬だって、実は運動が好きなのだ。
ただし、人の暮らしに合わせて生活していると自由に体を動かす機会は減っていき、運動の楽しさまでも忘れてしまうことがある。
愛犬の心身の健康を守るため、運動にまつわるあれこれを知っておこう。

犬にとってアジリティは競技ではなく遊び
練習を始める前に、飼い主さんがしっかり認識しておきたいことがある。それは、「犬はスポーツをしたいわけではない」ということだ。
犬にとってスポーツは、すべて人と一緒に楽しむ遊び。楽しいからやりたいだけであって、「上達したい」「競技会で勝ちたい」といったモチベーションまで共有することは難しい。上達を目指す近道は厳しい訓練で能力を高めることではなく、犬を楽しませて「もっとやりたい」という気持ちにさせることなのだ。

練習する際の鉄則は、犬が飽きるまでやらせないこと。犬が自分からやりたがったり、人の顔を見て催促したりするなら、集中している証拠。反対に、周囲のにおいを嗅いだり体をポリポリかいたりし始めるのは「飽きちゃった」のサインだ。
集中力の持続時間には個体差もあるが、障害を越えるなどの「作業」そのものをさせるのは、最長で1分。できたらごほうびをあげるなど、犬の興味をつなぐ工夫を挟みながら繰り返す場合でも、最長で5分を目安にするとよい。
同じ理由で、できるまでやらせる必要もない。「成功して終わらせたい」というのは、人間の理屈。犬はルールを理解しているわけではないので、たとえハードルのバーを落としても失敗したとは思わないのだ。
最初のうちは、動きを教えるためにオヤツなどで気を引いてもよい。アジリティの作業(動き)は習慣で身につくもの。意欲的に繰り返すほど定着するのが早いので、ごほうびを上手に使って教えていこう。
また、犬が進んでやりたがらないのは、「やる気がない」せいとは限らない。するべきことがわからないために戸惑っている場合も少なくないので、飼い主さん側が教え方を見直してみることも必要だ。

日本犬×アジリティあるある
アジリティの障害は、日常生活では目にすることのないものばかり。犬の性格に合わせて、リードで誘導したりオヤツを使ったりしながら教えていこう。

好みの障害には、指示されなくても自主的にトライ!だって、自分のタイミングでやりたいから。
初めての障害とは柴距離をキープ。
「オヤツで釣る」が通用しない。
Aフレームにダダッと駆け上がり、頂点で止まって周りをグルリ。監視を終えたら、帰りは抱っこで。
スタートラインで「マテ」。スタートの合図と同時に、回れ右して脱走。
助走はかっこいいのに、障害の前でいきなりスンと急停止。
飽きちゃった瞬間、ごほうびも真顔でスルー。
シーソーの「ガタン」って音、なんとかなりませんか?

「これから先、何が起こるのか?」が予想できない時は動きません。
トンネルに入ってくれた!……けど、Uターンして「ただいまー」。
障害を上手に越えたら、そのままダッシュして練習場内をフリーランニング。
ポールの間隔、狭すぎない? と心の中でつぶやき、ポールにスリスリしながらスラロームをクリア。
カーブしたトンネルは苦手。見通しを立てたいタイプなので……。

監修:若林匡智先生
SJDフレンズドッグクラブ チーフトレーナー。
JKC公認訓練士、OPDES公認プロフェッショナルトレーナー。アジリティのレッスンを中心に、家庭犬のしつけも行う。アジリティ競技会の審判も務め、日本代表としてアジリティの世界選手権への出場経験もあり。
https://www.sjd.co.jp/dogclub/
Text:Kumiko Noguchi
Photos:Teruhisa Tajiri
Models:Tiberius、Tsukune、Vipsania
Shi-Ba Vol.135『愛犬と一緒!だから楽しい運動の極意』より抜粋