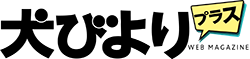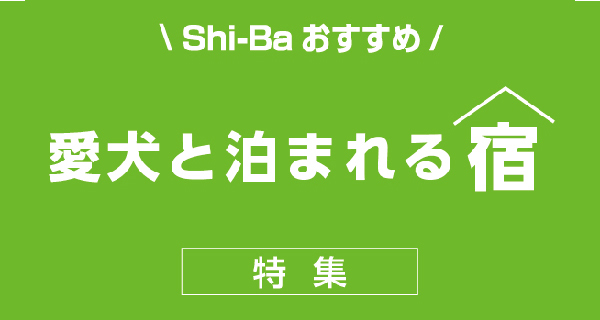今回は、ホルモンにまつわる代表的な病気を取り上げる。また、ホルモンバランスが乱れてしまう原因についても解説。ホルモンについてよく知らない人も、その働きについて学んでおこう。
【中級】ホルモンバランスって?

ホルモンバランスが乱れると体調が崩れてしまうのは人間も犬も一緒。バランスが乱れやすくなるのはどんな時なのだろうか?
Q.去勢・避妊でホルモンバランスに影響がある?
オスの精巣やメスの卵巣は性ホルモンの分泌に関わるが、去勢・避妊により、そこから分泌されるホルモンが急激に減ることで、体に大きな悪影響が及ぶとは考えにくいとされる。なぜなら卵巣や精巣を失ってもエストロゲンやプロゲステロンなどの女性ホルモン、アンドロゲンなどの男性ホルモンは他の器官からも分泌されているし、犬の一生は人間に比べたら短いので、去勢・避妊の影響が現れにくいと思われる。
Q.妊娠していないメスのヒート時期とそれ以外の時期の女性ホルモンの変化とは?
10ヶ月~1歳頃になると成犬になり、初めての発情期(ヒート期)を迎える。避妊をせず、妊娠してないメスなら、その後約7ヶ月ごとに発情期を迎える発情前期には卵胞ホルモン(エストロゲン)が増加し始め、やがて発情出血(便宜的に生理と呼んでいるもの)をする。発情期には黄体ホルモン(プロゲステロン)が一時的に増加するが、妊娠しなければ排卵後約30日で発情休止期の状態となる。
Q.妊娠中のメスの女性ホルモンはどのような変化を見せる?
排卵前期、卵胞ホルモン(エストロゲン)が増加すると、外陰部が大きくなり、発情出血が始まる。その約11日目後に排卵するが、このタイミングで交尾をすることで妊娠の可能性が高まる。妊娠すると黄体ホルモン(プロゲステロン)が妊娠期間中、多量に分泌され続ける(妊娠期間は58~63日)。妊娠後期、分娩時、分娩後1~2日後は、乳汁ホルモンのプロラクチンが高まり、分娩と授乳を助ける。

Q.去勢・避妊が体に及ぼす影響は?
精巣や子宮を切除することでホルモンのバランスは変わるので、太りやすくなることはある。オスは若い頃に去勢すれば、筋肉があまりつかず体はそれほど大きくならないケースも多い。メスの場合、避妊をしても性格などはほとんどの犬で変化しないが、ごく稀にオス化して気が荒くなったという犬がいる。それはホルモンが原因か性格やしつけが原因か判然としない。ホルモンの観点から見れば去勢・避妊は体に変化をもたらすが、中年期以降の卵巣や精巣の病気のリスクを減らす目的もあるので、健康上に悪影響を及ぼすとは一概にはいえない。ただし、オス犬の前立腺がんは極めて珍しい腫瘍ではあるが去勢で予防することはできない。
Q.人の女性と同じように更年期になるとホルモンバランスが乱れるもの?
人間の女性は50歳前後になると更年期に突入し、ホルモンのバランスが乱れ不調をきたすことが多い。個体差はあるが犬は10歳前後から妊娠しづらくなるので、この時期を更年期と捉えてもいい。なお「更年期障害」が犬にもあるのかはわかっていない。ちなみに加齢と共に犬のホルモンに関連する器官(卵巣や乳腺)において子宮蓄膿症や乳腺腫瘍などのリスクが高まる。それを回避するため若いうちに女性ホルモンに関わる器官、すなわち避妊手術をするのがよいとされる。
Q.ホルモンバランスの乱れを判断するために、動物病院ではどんな検査をするの?
ホルモン系の病気になった場合は診断が難しい。なぜなら他の病気と区別がつきにくいからだ。そこで、まずは問診をしっかりとり、次に視診や触診、聴診などの一般的身体検査を行う。皮膚病があれば、毛や皮疹の検査などを行う。この時点で、ホルモンが関与しているかいないかのおおよその判断をしている。そして、裏付けをとるために、血液検査、超音波検査、レントゲン検査、疑いのあるホルモンの検査などを行い、必要に応じてはCTやMRI検査、開腹検査も行う。検査の必要性が低いと判断された場合には省く検査もある。ホルモンの検査は院内で容易に行えるものから外注検査かつ取り扱いの困難な検査までさまざまである。いずれも高額な検査であるためいかに早く適切な診断を下せるか獣医師の力量がモノをいう。
Q.ホルモンバランスの乱れはどんな様子になって現れやすい?
ホルモンは相互作用するので、ひとつのバランスが乱れれば連鎖的に乱れ、それがさまざまな症状となって現れる。皮膚病に罹患したり、脱毛したり、体重が減ったり、逆に増えたりすることもある。また疲れて元気がなくなるだけでなく、心臓に負担がかかるなど生命に関わることもある。愛犬の様子がいつもと違い、それが長く続き、検査しても診断が下らない場合は、獣医師に相談し、ホルモン検査をしてみよう。
Q.ホルモンバランスが乱れる原因とは?
ホルモンバランスは精神的なストレスからも影響を受けるので、元気に健やかに暮らすことが大切。些細なことで乱れる場合もある。人間も同じだが規則正しい生活をして、ストレスを溜めないようにしよう。また、皮膚病などでホルモン剤を過剰に投与されて、バランスを乱すケースもあることを知っておこう。
【上級】ホルモン系の病気って?

ホルモンバランスの乱れが引き起こす代表的な病気を紹介。5歳以上で具合が悪そうならホルモン系の病気の可能性も視野に入れよう。
Q.犬に多いホルモン系の病気にはどんなものがある?
ホルモン系の病気は、(1)ホルモンが過剰に分泌される、(2)ホルモンの分泌が悪い、(3)ホルモンを分泌する器官に腫瘍ができるの3つに分類される。犬に多いのは、副腎皮質ホルモンが亢進する「クッシング病」、副腎皮質ホルモンの分泌低下で起こる「アジソン病」、甲状腺機能が低下する「甲状腺機能低下症」、生活習慣病のひとつ「糖尿病」、避妊してないメス犬の「子宮蓄膿症」「卵巣囊腫」が挙げられる。
Q.副腎ホルモンが亢進するクッシング病ってどんな病気?
副腎皮質で起こる病気で、本来は「副腎皮質機能亢進症」ともいう。多くは下垂体腫瘍で発病するが、皮膚炎の治療のためホルモン剤を長期・多量投与した場合でも起こることがある(これを医原性という)。糖質コルチロイドの一種、コルチゾールというホルモンが持続的に分泌されてしまうことが原因だが、このコルチゾールは糖質や脂質の代謝に関わる大切なもの。そのため代謝に異常が発生する。6歳以上の犬に多い。
Q.クッシング病の犬に見られる主な症状とは?
初期は、食欲がありよく水を飲む肥満気味であるだけのためほとんどの飼い主は病気だと思っていないが、獣医師が見るとクッシング病だと一目見てわかることが多い。やがて被毛が薄くなり足が震え、お腹もたるむ、靱帯を容易に切ってしまう、糖尿病を併発する。さらに、皮膚が薄くなり血管が浮き出るようになる、感染性皮膚炎が治らない、呼吸が浅く早くなる、動脈内血栓が詰まり突然死することもある。メスにやや多く見受けられるが、日本犬には少ない。
Q.クッシング病と診断されたらどんな治療を受けるの?
臨床症状、血液検査、超音波検査そしてACTH刺激テスト(コルチゾール分泌量テスト)でほとんど診断がつくが、下垂体性なのか副腎腫瘍なのか医原性なのかを鑑別するために追加検査を行うこともある。治療は一般的にコルチゾールの分泌を抑える薬の投与が治療の中心となるが、手術や放射線治療により腫瘍を取り除いたり、小さくしたりすることが可能な場合は、それらの方法も選択される。ホルモン剤の薬が引き金になっているようなら、投薬を一時的に休止して様子を見ることもある。
Q.副腎ホルモンが低下するアジソン病ってどんな病気?
クッシング病とは反対に、副腎皮質ホルモンの分泌が低下することで起こる。和名は「副腎皮質機能低下症」という。免疫機能の異常が主な原因であるが、感染症などが原因となることもある。下垂体腫瘍や薬物などによる二次性副腎皮質機能低下症も時に見られる。

Q.アジソン病の犬に見られる主な症状とは?
元気がない、食欲がない、震えている、下痢~血便、嘔吐、吐血、腹痛、低体温、徐脈、水をたくさん飲む、多尿になる、無気力になるなど。6歳以下のメス犬に多く見られるが、日本犬には少ない。アジソン病の症状は、特にこれといった特徴が見られないので判断が難しい。「副腎クリーゼ(急性副腎不全)」といって、アジソン病の犬に大きなストレスがかかると、低血糖と体内のナトリウム低下を引き起こしてショック状態となり、突然死することもある。
Q.アジソン病の治療法を教えて
アジソン病は特有の症状が見られないため、診断にはアジソン病を疑い、検査をする。一般的には血液検査で低ナトリウム・高カリウム、レントゲン検査で心臓、後大静脈径、肝臓の退縮が見られ、心電図検査も異常になっていればほぼ間違いないが、二次性の場合には見られないので確定診断はACTH刺激テストで行う。治療は重症度によって変わるが多くは入院させて集中治療から始める。症状が改善して退院できたならば、アジソン病治療薬を毎日投与していく必要がある。
Q.甲状腺機能低下症ってどんな病気?
甲状腺の機能が低下する病気。人間でいうと橋本病に似た免疫疾患で、原因は主に甲状腺自己抗体が甲状腺組織を攻撃・破壊する「自己免疫反応」、あるいはリンパ球性甲状腺炎、甲状腺の萎縮など。ちなみに甲状腺低下症とは逆の「甲状腺機能亢進症」(人間でいうとバセドウ病)は、ネコに見られるが犬で罹患するのはごく稀とされる。
Q.甲状腺機能低下症に見られる主な症状とは?
元気がなくなる、疲れやすくなる、動作が鈍くなるなど動きに変化が現れる。体の左右対称の脱毛や、皮膚が乾燥してフケが多くなるなどの皮膚疾患が目立つ。さらに基礎代謝が低下するため、寒がったり、体重が増えたりすることも多い。メスの場合は発情期のサイクルが乱れることも。また糖尿病やアジソン病などのホルモン系の病気を併発しやすくなる。早く発症する犬は3歳からで早期発見が治療のカギとなる。メスの柴犬は罹患しやすいので注意が必要。
Q.甲状腺機能低下症の治療法を教えて!
血液検査やエコーなどにより診断される。治療には甲状腺ホルモンを補うホルモン剤の投与が有効とされている。しかし甲状腺ホルモンの低下は、甲状腺機能低下だけが原因でない場合もあるので(糖尿病、肝不全などの可能性もある)、正しい診断のためには、外部検査センターでしか行えない、fT4,T4, TSHなどを調べて見極める必要がある。T4だけの検査は投薬効果をみる指標にはよいが診断には不足である。診断をつけず、あるいは誤診をして甲状腺ホルモン剤を投薬すると命に関わることがある。なお甲状腺機能低下症の治療は一生続けていく必要があるが、投薬で症状は安定する。
Q.治療に伴うホルモン剤などの副作用が心配
副腎皮質ホルモンから生成された「ステロイド剤」は、アトピー性皮膚炎などの炎症を抑える軟膏や抗炎症剤として幅広く投与されている。目覚ましい効果を挙げている一方で「ステロイド剤=副作用が怖い」と躊躇する飼い主も少なくない。副作用が出ることは否めないが非常に高い効果を発揮するのも事実。獣医師に相談し、愛犬の状態を見ながら正しく服用しよう。
ホルモンの病気は珍しいが……

今回は、ホルモンにまつわる代表的な病気を取り上げたが、ホルモンに関連する病気はここに紹介したもの以外にもたくさんある。有名な糖尿病を筆頭に、抗利尿ホルモンが影響で尿のコントロールができなくなる「尿崩症(にょうほうしょう)」、上皮小体ホルモンの不足で骨がもろくなったりする「カルシウムの代謝異常」、犬の健やかな発育を助ける「成長ホルモンの分泌異常」などもある。
また病気ではなくても睡眠リズムに関わる「メラトニン」、授乳期のメスの乳腺に作用して乳汁を出す「プロラクチン」など、必要に応じて分泌されるホルモンも少なくはない。
先述したとおり犬の体内には、さまざまなホルモンが分泌されており、それぞれは単独ではなく相互作用によって働く。精巣や卵巣から分泌される性ホルモン以外、例えばインスリンや甲状腺ホルモンなどは、分泌されなければ薬などで与え続けなくてはならない。
焼肉屋のホルモンは「放るもん(捨てるもの)」であることから、その名がついたという俗説もあるが、犬にとってホルモンは放っておけない大切なものなのだ。しかしホルモンにまつわる病気の判断は難しい。にもかかわらず適切な治療には早期発見が望ましいとされる。
毛が抜ける、元気がないなど、愛犬が今までとは違った様子なら、ホルモン系の病気を視野に入れてもよさそうだ。その些細な変化に気づけるのは飼い主しかいない。普段から愛犬と触れ合いを大切にしている飼い主ほど異変を早めにキャッチできるだろう。
関連記事:知っているようで意外と知らない。犬のホルモン 30の質問【初級編】
人気のキーワード:
#しつけ #ごはん #シニア犬 #健康管理
#性格 #散歩 #気持ち #病気 #おでかけ
#ケア #子犬 #性別
Shi‐Ba vol.83『「バランスの乱れ」はよくないと聞くけど意外と知らないその役割とは!?気になるホルモン30の質問』より抜粋
※掲載されている写真はすべてイメージです。